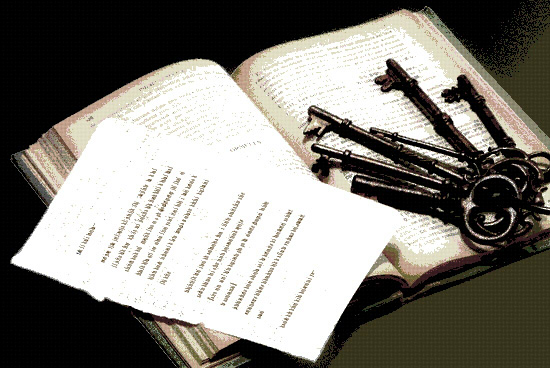〜真実の一端〜 章1 『流(りゅう)』を認め、『留(りゅう)』を求め―― かつて此の地は、絶え間なく続く戦火によって荒廃の窮みに陥っていた。 尽きせぬ欲望の赴くままに他者を喰らい蹂躙する事しか知らず、無知と無恥によって世界をも道連れに滅びの道をひた走る人間たち。 度し難い浅ましさを晒す醜き人類に下された、形を成した審判の鉄槌。それが、かの存在の原義だとも云われる。 もっとも、理由や原因の如何を問うことに意味は無い。ただ事実として、世界が人の手になる破滅の瀬戸際に立たされていた時、それは何処からともなく忽然と現れた。 人はそれを形容するだけの言葉も、それを認識するだけの知覚も、それを理解するだけの概念をも持ち合わせてはいなかった。 ごく初期には、自らの無知を臆さず受け容れる度量を備えた一部の識者が、かの存在を『アグノーストス(不可知なるもの)』と呼んだ事もある。 だがそれすらも、人間の矮小で未発達な宇宙観に未知なるものを無理矢理当て嵌め、貶めようという驕慢の産物でしかなかった。 かの存在を前にして、人は自らが塵埃に等しい無力な生き物である事を知った。 無数の干戈と蛮声は、その咆哮一つで血河と化して渇いた大地を潤し、姑息な奸策と謀計も、その巨躯に唯ひと筋の傷を付ける事さえ適わなかった。 反面、その雄壮が身を安らえた場所では、刈り尽くされた樹々や踏みにじられた草花が急速に新たな芽吹きを迎え、生きる場所を失っていた動物たちが導かれるようにして群れ集い、牧歌的としか言い表せぬある種の理想郷を体現した。 どこかで大きな争いが起これば六枚の翼で天空より飛び来たりて、勢力の如何を問わず人々を跡形もなく根絶し。 どこかに荒れ果てた地があれば強靱なる魁偉を悠々と横たえ、安寧に満ち生命の溢れる小さな楽土を現出させる。 絶対的な破壊の力と、超常的な再生の力。相反する二つを共に宿したその在りように、やがて人は大いなる流転の力――即ち『流(りゅう)』を見出すに至る。 そして、歴史的な転機もまた、唐突に訪れた― とある国の統治者たる男が、その取るに足らぬ筈の噂を耳にしたのが、全ての始まり。 『かの荒神の下へ群れ集う動物たちに混じるようにして、人の子の姿が確認されることがある』 有り得ぬ話だった。様々な理由から、多くは欲望の命ずる儘、かの存在に近づこうとする人間は後を絶たなかったが、そうした人間たちには等しく死という報いがもたらされたし、心清き無辜の人々であれば、今や恐怖の象徴たるかの存在に敢えて近づくような真似をする動機が無い。 結果、「近づけば死あるのみ」というのが、その頃には周知の事実となっていたのだから。 しかし、人一倍強い好奇心をも持ち合わせていたその王は、ほんの気紛れで噂の真相を自らの眼で確かめる事にした。 斯くして、後に『封印の歌姫』と呼ばれる歌い女の一族が歴史の表舞台へと浮上し、同時に裏舞台へと隠蔽されるに至る。 理由や原因の如何を問うことに意味は無い。ただ事実として、その一族の女が繰る『歌』だけが、かの存在に意思を伝達し、従わせる力をも秘めていた。 そして王は、かの存在を永劫に自らの統治する地へ押し留め、もたらされる豊穣と繁栄を恣にする野心――即ち『留(りゅう)』を望むに至る。 そして、強大な力を持つかの存在は、暗い地下世界へと繋ぎ止められた。 時は流れ、事の真相を知る者は世界最大の強国となった国の王位継承者と、その国に仕える一握りの識者のみとなって久しい。 ただ、伝承に謳われるかの存在の名だけは、認められ、求められたままの音を残し、こう呼ばれた。 その威容、聳え立つ巨大な甲殻たるを表す字を当て嵌め――即ち『竜(りゅう)』という名で。 |